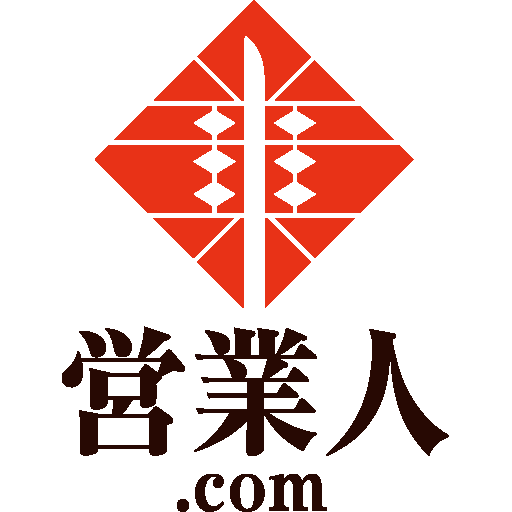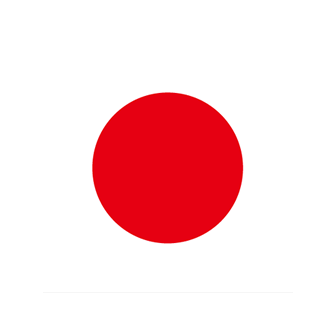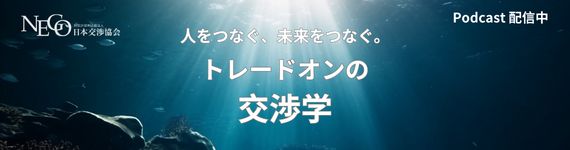営業のあり方(Being)を考える~論語営業のすすめ②
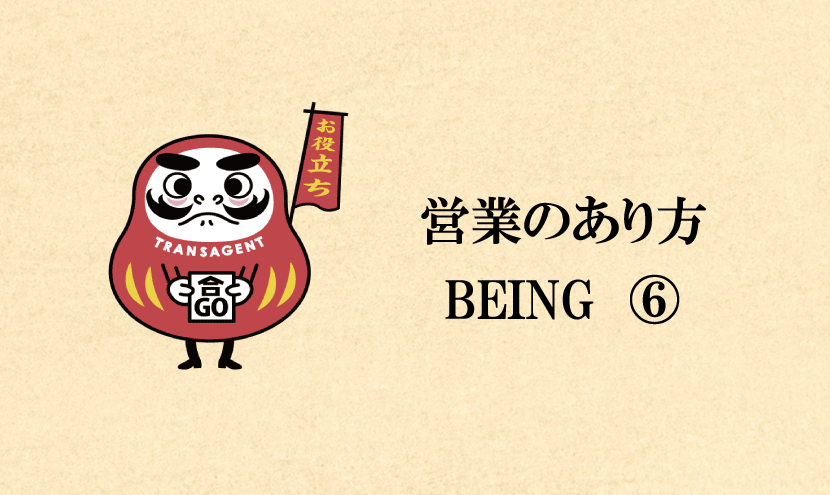
営業人.com代表 安藤 雅旺
営業のあり方(Being)を考える~論語営業のすすめ②
営業にとって大切なことは何でしょうか。この問いに対する答えは千差万別であります。
大切なことは自らの経験から仮説をしっかりと持つことだと思います。どうすれば売上げを上げられるようになるのでしょうか? 日々の営業活動でやりがいを高め、仕事に積極的に取り組むことができるようになるには何をすればよいでしょうか? 行動量を増やし持続力を高めるために何ができるでしょうか? どうすれば営業のレベルを上げることができるでしょうか? このような問いに対して、自分なりの答え、仮説を導き出すためには自らの拠り所となる信念を持ち、自身のあり方(Being)の軸をしっかりと固めておくことが重要になります。いくら立派な家を建てても土台がしっかりしていなければ、大きな地震に遭遇するとすぐに倒壊してしまいます。『後漢書』に「疾風に勁草を知る」という言葉があります。激しい風に見舞われた時に初めて本当に強い草かどうかが分かるという意味です。営業として疾風に遭遇した際に自身が勁草になっているかどうかを決めるのは自分の中に信念や在り方(Being)の軸が定まっているか否かなのです。
営業とは、失敗の積み重ねの上に成り立つ仕事です。新規開拓であれば相手に断られるのが前提です。新規の成約を勝ち取るにはそれなりに多くの失敗(断られる件数)を経験していく必要があります。そのため失敗を恐れ、なるべく失敗を避けて通りたいと考えている人には務まらない仕事であるといえます。また時としていわれなきクレームやトラブルに見舞われることもあります。そうした際にも、慌てることなく平身低頭で相手の立場に立ち、相手の置かれている状況を理解し、謝罪し、誠意をもって対処する必要があります。会社の代表として顧客に対して責任を自ら負う姿勢が求められます。そうした意味では強い当事者意識と責任感を持ち、精神的にタフでなければ務まらない仕事でもあります。こうしたことから営業には、強い精神力・行動力・持続性・忍耐力・積極性・寛容さ・謙虚さ・感謝の気持ちなど人間性に関わる側面が強く求められるのです。人間性の向上が営業力の向上につながるといっても過言ではありません。
人間性を向上させるために役立つ書として『論語』があります。『論語』とは孔子が人としてのあるべき道について述べたことを後に弟子たちがまとめた書のことです。
日本資本主義の祖である渋沢栄一は、仕事をする上での在り方として「士魂商才」の重要性を説き、士魂や商才は『論語』によって養われると主張しました。『論語』は人間性の向上のみならず商才を磨くことにも有益な書であるというのが渋沢栄一の考えです。そうであるならば営業力を向上させるためには士魂商才を養う『論語』を学び実践していくことがその近道になるはずです。『論語』を営業に当てはめて考え、行動することで、自らの拠り所となる信念を作り上げ、自身の在り方(Being)の軸をしっかりと固めることにつなげていけるのです。
商い・営業のこころ
営業の在り方(Being)を考える上で、大いに参考になる映画があります。1984年に製作された『てんびんの詩』という映画です。近江の豪商の家に生まれた主人公が、小学校の卒業祝いとして父親から鍋蓋を渡されます。そして鍋蓋を売ることができなければ家業は継がさないといわれ行商の旅に出る物語です。主人公は悪戦苦闘し最初は知人に頼み込み押し売り同然で買ってもらおうとしますがうまくいきません。上辺だけ愛想よく振りまいてみたり、わざとみすぼらしい姿にして人の同情を乞うやり方をしたり、親に虐待されているとうそをついたり、手を変え、品を変え、自分本位な売り方を繰り返していきます。しかし誰も相手にしてくれません。行く先々で断られ続ける中で、ついには自暴自棄になり、放浪し、行き詰まっています。そしてついにはたまたま目にした外に置いてある他人の鍋蓋を見つけるやいなや「これをいっそのこと破壊して、困らせて売ればよいのではないか」という蛮行を思いつきます。そしていよいよ行動に移そうと試みますが、直前で自らの良心によって思い留まります。それは「目の前の鍋蓋も自分と同じ他の誰かが苦労して売って、それを買った人が大切に使い込んだものだ、誰かに作られて長い旅をして買われ、ここまで使われたものだ」ということが頭をよぎったからでした。そして自らの行動を恥じて、一転その鍋蓋をきれいに磨き始めます。それを見た鍋蓋の持ち主の女性が主人公の不審な行動について問いただします。主人公は破壊しようとしたいきさつを正直に話し心からお詫びをします。鍋蓋の持ち主は正直に謝罪し、心をこめて鍋蓋をひたすら洗っている少年の姿を見て、不信感を捨て、許し、逆に鍋蓋を買ってあげる、売って欲しいと言い出します。少年は予想もしていなかった展開で鍋蓋を売ることができ、その後もお客さんがお客さんを連れてきてくださり、すべての鍋蓋を売ることができたという物語です。ここではまだ少年である主人公が鍋蓋を売ることを通して、自己中心的な姿勢を改め商いでもっとも大切な相手の立場に立つ心「仁の精神」について学んだことが描かれています。営業の在り方を考える上でもっとも重要なことはこの『てんびんの詩』の主人公にあるように自分本位の考えを捨て相手の立場に立って考える、「仁の精神」を持つことであると言えます。この重要性を説いた書が『論語』であり、『論語』を経済活動を行う上で、中心に据えて学び実践しなさいと述べたのが、日本資本主義の父である渋沢栄一なのです。
安藤 雅旺 プロフィール

株式会社トランスエージェント 代表取締役
NPO法人日本交渉協会 代表理事
二松学舎大学大学院国際政治経済学研究科修士課程修了
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科修士課程修了(経営管理学修士MBA)
株式会社ジェック(人材開発・組織開発コンサルティング業)での営業経験を経て独立。
2001年株式会社トランスエージェントを設立。
2006年上海に中国法人上海創志企業管理諮詢公司を設立。
「仁の循環・合一の実現」を理念に、マネジメント・イノベーション支援事業、
交渉力・協働力向上支援事業、BtoB営業・マーケティング支援事業を展開している。
主な論文・著書
「中国進出日系企業の産業財市場における顧客インターフェイスの研究」
Strategy for Managing Customer Interface taken by Japanese B to B Marketers in China
~Effective Business Activities in Developing Customer-Supplier Relationship in China~
(立教大学大学院MBAプログラム2011年度優秀論文賞受賞)
『心理戦に負けない極意(共著)』(PHP研究所 2009)
『中国に入っては中国式交渉術に従え!(共著)』(日刊工業新聞社 2013)
『交渉学ノススメ(監修)』(生産性出版 2017)
『論語営業のすすめ』 (生産性出版 2021)
『论语和营业人』 (今日出版 2025)
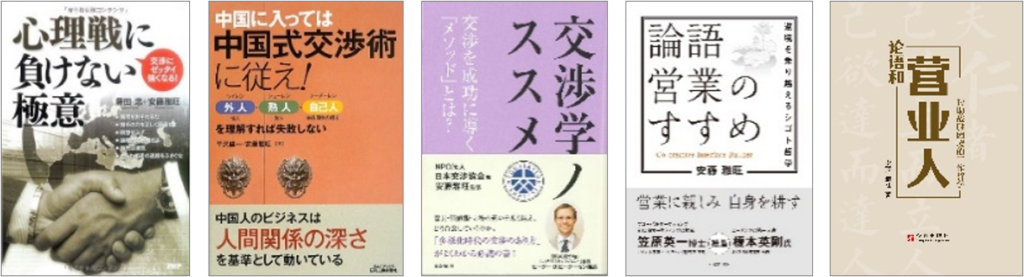
本誌掲載の写真 ・ 記事 ・ 図版を無断で転写 ・ 複写することを禁じます。