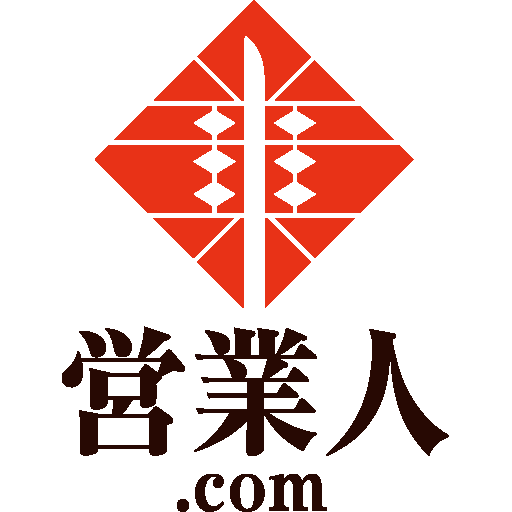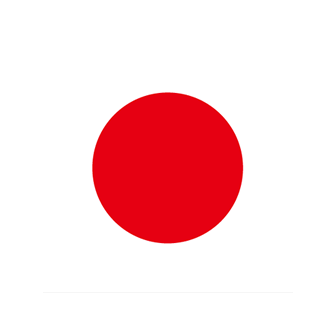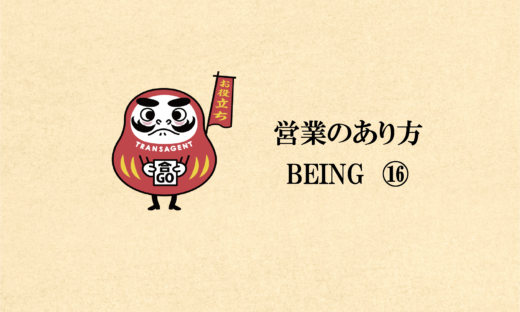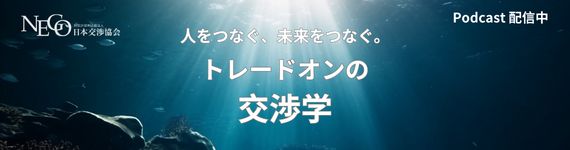士魂商才の磨き方~論語営業のすすめ④
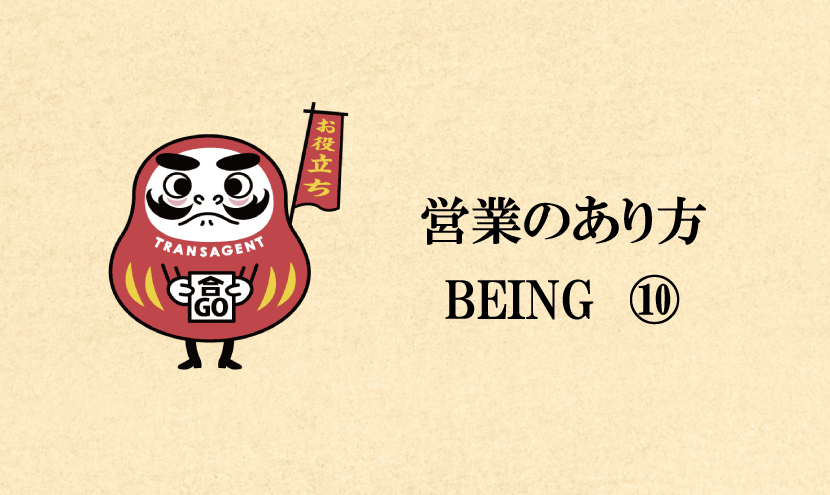
営業人.com代表 安藤 雅旺
士魂商才の磨き方~論語営業のすすめ④
士魂商才を養うには『論語』を学べと渋沢栄一の教えにあります。『論語』とは儒教の始祖である孔子の教えを弟子達がまとめた書で紀元前5世紀頃のものです。道徳を説いた書で平たくいえば人間としての生き方について説かれた書です。孔子や弟子たちの言行録としてまとめられています。
2500年以上前のものですから当然解釈に唯一絶対の正解というものはありません。人間としての在り方について祖述し、実践することこそ真の学びになります。学問のための学問、論語読みの論語知らずになってはまったく意味がありません。そのため『論語』を現在に生きる営業人である我々が実際の仕事の実践に役立つ形に翻訳する、現代の営業人の視点で解釈し活用していくことが士魂商才を磨くことにつながると考えます。よりよく生きるための書『論語』をよりよく営業するための書として活用するのです。
渋沢栄一は『論語』の学び方について『論語講義』の中で知行合一の精神を持って論語を学べと述べています。
学問は学問のための学問にあらず、人間日常生活の指南車たらんがための学問なり。(中略)余は実にこの知行合一の見地に立ちて、論語を咀嚼し八十四歳の今日まで公私内外の規準として遵奉し、国を富まし国を強くし以て天下を平らかにするに努力したり。他の同胞実業家にも論語をよく読んで貰い、民間に知行合一の実業家ぞくぞく排出して、品位の高き先覚者が出現せんことを望むのである。
知行合一は陽明学の有名な教えの一つで言葉は平易ですが内容は大変難しい概念です。ここで渋沢栄一が言いたかったのは、実践に根ざした学びである必要性です。『論語』を暗記することや、字句の解釈に学びの中心を置くのではなく、自らの日常や仕事に生かし、自分の人間的成長を促す実践の学問として学習するのです。知行合一で知られる陽明学は15世紀明の時代に王陽明が打ち立てた儒教の一つです。『論語』とあわせて『陽明学』も学ぶことが士魂商才を磨くことにつながると思います。士魂とは武士の精神でありますが『武士道』の著者新渡戸稲造は、陽明学も武士道の淵源の一つでもあると述べています。渋沢栄一の『論語』を知行合一の精神で学ぶという言葉に従い『論語』と陽明学の教えを学ぶことが士魂商才を磨くことにつながると思います。
論語営業のすすめ
『論語』ではさかんに小人と君子という言葉が対比されて出てきます。小人とは徳のない人を指し、君子とは徳のある人を指すと解釈すると、徳の低い自己を省みて徳を高めるというのが目指すべき大きな方向性になります。私自身そうですが、小人である自己をいかに変革し徳を高めていくことができるかということが大きな課題設定になるのです。
営業が人間力向上に寄与する仕事であるということはすでに述べましたが、『論語』を拠り所とした営業を「論語営業」と定義すると「論語営業」の目的は、営業という仕事を通して自分自身の人間性を高めること、つまり小人である自己を少しでも君子レベルに近づけることです。これまで営業の目的として捉えられてきた商品・サービスを売る、売り上げを上げる、顧客を開拓する、顧客の課題解決、問題解決を支援する、顧客のビジョン実現を支援するなどといった役割・目的と並行して、「顧客創造活動を通して自身の人間性を高める。そして自身を小人から君子へ近づけること」と営業の目的を定義することを提案したいと思います。そう考えると普段の営業活動がより壮大な問いに挑む仕事になります。また日々の仕事をどのような状況に置かれてもぶれない強い自己を創る糧とすることができます。
はるか昔学問をすることの目的は自身の人格形成にありました。徳を修めることが土台にあり、その上に個性を生かした専門技術を磨くというものです。現代はもはやこうした考えは消えてなくなりつつあります。しかし、昔も今も自身の人格形成が重要なことは変わりありません。陽明学の王陽明は事上磨練という言葉を残しています。これは学問について日々の行動・仕事・実践を通して自身を磨こうとすることが真の学問であるという考え方です。
そうしたことに鑑みると、営業という仕事に対して「論語営業」を志向することで、営業活動を通して自身の徳を高める、自己の人格形成を行うといった目標設定・目的意識を持つことで、自己成長につながり、日々の仕事にやりがいが生まれると私は考えています。徳を磨く、自己の人格形成というと「立派な人間になりなさい」といった堅苦しい印象を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。しかしここで言う徳を磨くとは「立派な人間になりなさい」というような外側から測られるものさしではありません。あくまで自分との対話であり、自らの内側から測るものです。「恥を知り自らの良心に従う」「本来の自己を見出し、自己らしさを発現する」「自己の使命を果たす、一隅を照らす」「人生の質を高める。充実した人生を過ごす」こうしたことを目指すことだと捉えています。そして何よりも楽しむこと、楽しめるようになることが大切なことなのです。
これを知る者はこれを好む者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如かず。『論語』(雍也第六)
知っているというのは好むのには及ばない。好むというのは楽しむのには及ばない。(『論語』金谷治訳注 岩波書店)
論語営業解釈:
営業を知っている人は営業を好む人には及ばない。営業を好む人は営業を楽しんでいる人には及ばない。
安藤 雅旺 プロフィール

株式会社トランスエージェント 代表取締役
NPO法人日本交渉協会 代表理事
二松学舎大学大学院国際政治経済学研究科修士課程修了
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科修士課程修了(経営管理学修士MBA)
株式会社ジェック(人材開発・組織開発コンサルティング業)での営業経験を経て独立。
2001年株式会社トランスエージェントを設立。
2006年上海に中国法人上海創志企業管理諮詢公司を設立。
「仁の循環・合一の実現」を理念に、マネジメント・イノベーション支援事業、
交渉力・協働力向上支援事業、BtoB営業・マーケティング支援事業を展開している。
主な論文・著書
「中国進出日系企業の産業財市場における顧客インターフェイスの研究」
Strategy for Managing Customer Interface taken by Japanese B to B Marketers in China
~Effective Business Activities in Developing Customer-Supplier Relationship in China~
(立教大学大学院MBAプログラム2011年度優秀論文賞受賞)
『心理戦に負けない極意(共著)』(PHP研究所 2009)
『中国に入っては中国式交渉術に従え!(共著)』(日刊工業新聞社 2013)
『交渉学ノススメ(監修)』(生産性出版 2017)
『論語営業のすすめ』 (生産性出版 2021)
『论语和营业人』 (今日出版 2025)
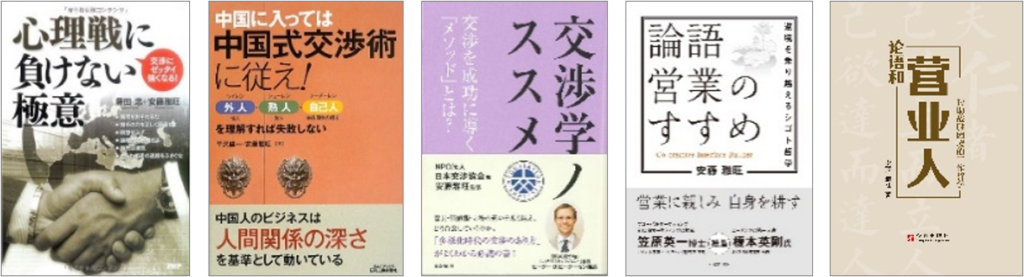
本誌掲載の写真 ・ 記事 ・ 図版を無断で転写 ・ 複写することを禁じます。