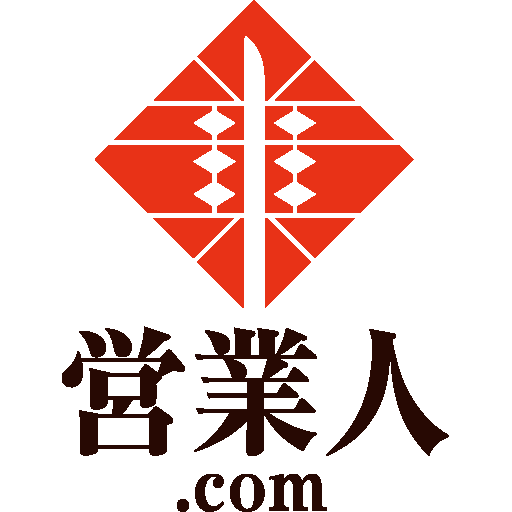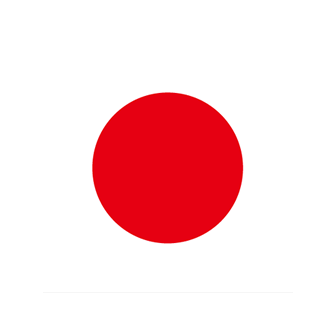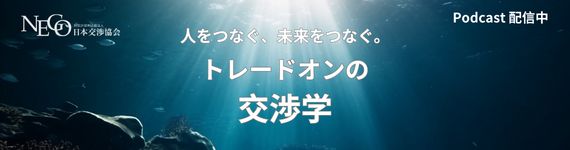Vol.12 中国における「高かろう、よかろう」戦略の終焉から見直す自社の価格戦略

中国市場では、かつて「高かろう、良かろう」戦略が外資系企業の成功の鍵でした。高価格を高品質の象徴とし、「海外ブランド=安心・安全・高品質」というイメージで消費者を引きつけ、ブランド優位性を築いてきました。しかし、SNSやECの普及により、価格や品質の透明性が求められる現代では、この「高かろう、良かろう」戦略が崩れ始めています。
1つ目の事例として、アイスクリームのハーゲンダッツを紹介します。
ハーゲンダッツは1996年に中国進出時、上海の一等地である南京東路に店舗を開業。平均月収500元(※当時のレートで約7,500円)の時代に、アイスクリーム1玉を25元=月収の20分の1(当時のレートで約375円)で販売し、「彼女を愛しているなら、ハーゲンダッツをごちそうしよう」というキャッチコピーで高級感を演出。贈答品市場でも人気を博し、ハーゲンダッツのアイス月餅は引換券が転売されるほど人気となりました。
ところが今年に入って、21時以降にはアイス「1個買うと、もう1個プレゼント」と実質半額のキャンペーンを展開しました。
また、コーヒーやカフェラテなどの飲料を60%以上値下げし、9.9元(現在のレートで約200円)で提供するなど、ラッキンコーヒーをはじめとした低価格帯のコーヒーチェーンのキャンペーン価格に匹敵する水準まで値下げをしました。
3四半期連続で店舗来店数が前年比2桁減となったこともあり「高かろう、良かろう」の維持よりも「お手頃感」を打ち出して客数の回復を図る狙いがあります。
2つ目はスターバックスの事例です。
スターバックスは2025年6月、中国進出から25年目にして初めて、一部商品の定価の引き下げに踏み切りました。
対象はフラペチーノやアイスティーなどの非コーヒー系商品で、約5元(約100円)の値下げを実施しました。既存店売上が2025年度第1四半期まで、4四半期連続で減少したこともあり、こちらも値下げにより来店客数の回復を狙っていると考えられます。さらに、スターバックスは2024年11月から中国事業の一部売却について検討中と公表しており、今後の事業ポートフォリオ見直しと関連づけた価格戦略の一環とも見て取れます。
3つ目は、最近、中国市場からの撤退を発表したくら寿司の事例です。
日本を代表する回転寿司チェーン「くら寿司」は、2023年に上海で中国1号店をオープンし、10年で100店舗を目指す計画を掲げました。しかし、2025年6月にわずか3店舗で撤退を発表。
様々な要因の中の1つに価格戦略の失敗があげられます。1皿12元(約240円)の価格設定は、日本の価格115円の2倍以上で、中国消費者から「割高」と見なされました。
12元という価格に対して、私はその品質に満足していました。ただし現地では、競合の回転寿司チェーンが同価格帯でラーメンや鍋などの豊富なメニューを提供しており、多くの中国人消費者の支持を集めました。その結果、くら寿司は採算ラインに乗せることが難しかったようです。
この3つのブランドとも中国では本国より高い売価設定をし、高級路線で成長してきました。
この「高かろう、良かろう」が通じなくなってきた背景には情報環境の変化があります。
現在では、SNSを開けば各国の販売価格を簡単に比較できるため、「なぜ中国だけ価格が高いのか」といった疑問はすぐに浮かびます。たとえ本国以上に調達原価やその他コストがかかっていたとしても、消費者がその事情を考慮してくれるとは限りません。
さらに、インターネット検索によって、自分の嗜好に合った良質な店舗をいくらでも見つけられる時代です。その結果、「高級=誰もが憧れる特別な体験」といった、価格に基づく期待価値は、以前にも増して通用しにくくなっています。
新しい市場に進出する際には、本国の商品を単にコピーするのではなく、なぜ本国で成長できたのか――たとえば「コストパフォーマンスの高さ」などの成功要因を抽出し、それを現地でどう再現するかを考えることが重要です。
【日本のBtoB営業人にとっての洞察】
中国市場の事例から、日本のBtoB営業人が学べることは、「自社の価格戦略の再評価」「購入品の適性価格の再評価」「現地適応」だと考えています。
1.価格戦略の再評価について
インターネットやAIの普及により、価格の透明性が向上し、顧客は競合や海外製品と容易に比較できます。「少し高いが、サービスも良いし、信頼できる」という評価は、ずっと続くとは限りません。
また、コスト高で自社の粗利率を削って価格維持をしていたとしても、その努力は、なかなか顧客には伝わりません。顧客の視点に立って自社の価格が相対的にどう位置づけられているかを常に把握し、もし競合と比べて高いのであれば、その理由と付加価値を説明していく必要があります。
さらに、たとえ自社が「顧客のため」と思ってコストをかけて提供しているサービスであっても、顧客がそこに価値を感じていないのであれば、提供内容を見直し、コスト削減による価格調整を検討すべきかもしれません。あるいは、そのような付加価値に対して追加費用を払ってでも求める企業に対し、営業戦略をシフトさせる判断も重要です。
2.購入品の適性価格の再評価
同じ理由で、他社から購入している商品やサービスについても定期的に価格と得られるベネフィットを定期的に見直すことが重要です。特にサービス分野では、新興企業がAIを活用し、従来の常識を覆すような価格帯でサービスを提供している可能性もあり、注意が必要です。もちろん価格だけで判断すべきではありませんが、アンテナを張っていることにより既存の仕入れ先との交渉において有利に働くこともあります。
3.現地適応の徹底
くら寿司の撤退は、日本の成功モデルをそのまま移植したことにあります。BtoB営業でも、顧客の業界やニーズに合わせたカスタマイズが不可欠です。
特に自社の既存商品を新しい業界、新しい地域で展開する場合に、成功モデルをそのまま適用する前に、成功モデルのエッセンスを、抽象度を高めて理解し、そのエッセンスを新しい市場・ターゲットにどのようにあてはめていくのかを考え、徹底していくことが大切です。
野村義樹 プロフィール

愛豊通信科技(上海)有限公司 副総経理
中国駐在員に人気のメルマガ「中カツ!通信」の配信者
1978年、東京生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒。政府奨学金留学生として天津の南開大学に留学。日本帰国後コンサルティング会社に入社。台湾、深センの駐在を経て、カゴメ株式会社に転職し中国での食品事業、EC事業、食堂事業に携わる。その後、現職にてシニア向け事業の立ち上げ後、コールセンター、EC代理運営、BtoB営業支援を日系企業、欧米企業、中国企業向けに提供。
毎週、中国市場を面白く紹介する「中カツ!通信」を3,000名以上の登録者に配信。約20年に渡り中国の発展を見てきた経験と「現場」の情報は、記者やエコノミストも注目している。