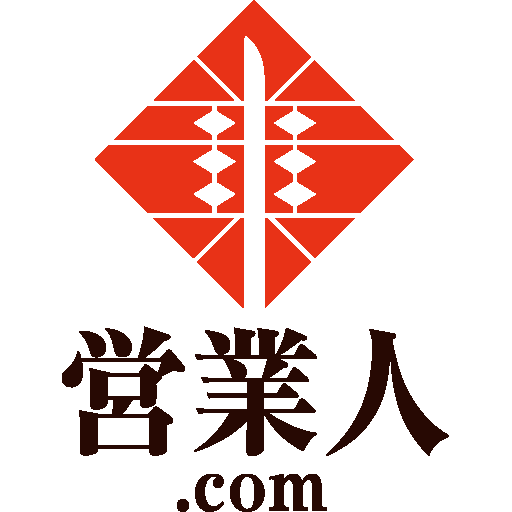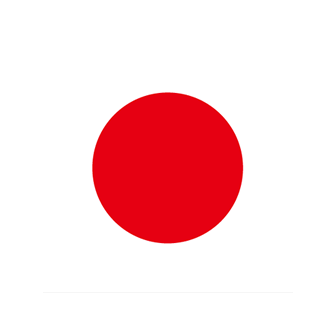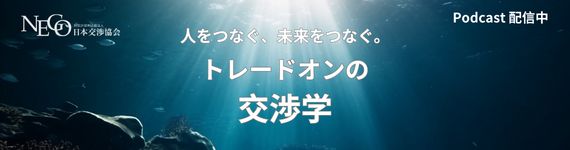Vol 7. 贈り物に値段をつけて価値を伝えよう

中国の春節(旧正月)は、民族大移動とも呼ばれる大きな社会現象です。以前は都市に出稼ぎに来ていた人が故郷に帰省する際に田舎では手に入らない都市のお土産を抱えて帰るのが習慣でした。私も10年前、妻の実家に帰る際、親戚への挨拶回り用に日本のクッキー詰め合わせを10箱爆買いしました。重くてかさばるお土産を持って列車で移動する苦労も「食べたことない!ありがとう!」と笑顔で喜んでもらえれば報われたものです。時代は変わり、特にECと物流の発展により現在ではスマホで簡単に贈り物を送ることができるようになりました。中国では贈り物において「面子」が重視される文化があり、贈り物の選び方にも細かな配慮が求められます。15年前、私が中国人社長から教わった取引先に贈るプレゼントのポイントは、「片手で持てない、重さと大きさのものを選ぶ、値札はつけたままにする」というものでした。値札はつけたままとはいえ、実際には割引価格で買っているので値札も面子を重んじるための一つの手段だったのです。同時に中国では「紅包」と呼ばれる現金を贈る習慣もあります。ご祝儀やお年玉といった場面だけでなく、便宜を図ってくれた相手への謝礼としても、今でも用いられています。(不正防止政策で表向きには減ってきている)
【この事例を日本でどう活かすか?】
贈り物をしよう
矢野経済研究所によると2022年のフォーマルギフトといわれる中元・歳暮市場は0.8%減だそうです。確かに儀礼的だったり義務的だったりするお中元、お歳暮はビジネスとしての効果は低いかもしれません。ただ企業間で贈り物文化が残ってきたのは、ビジネスとしての効果があったから、ここまで続いてきたともいえます。
現在は多様化の時代であり、モノよりコトの時代であります。定番品以外にもストーリーがある商品がたくさんあります。
贈り物をする人が減っている今だからこそ、なぜこの商品を贈るのか、その理由まで伝えることができれば、差別化にもなり、相手にも喜ばれるはずですし、ビジネスにも良い効果をもたらすでしょう。
また「儀礼的」から脱するためには、あえてお中元、お歳暮の時期を外して、「初めての商談が成立した日」「送り先の企業の創立記念日」「担当者の誕生日」など相手が特別感を感じる日に贈ると更に効果が期待できそうです。
値段をつけて贈り物をしよう。
「贈り物をしよう」とはいったものの、実際には社内予算の問題もあります。毎回、自腹もキツイですよね。
そこで中国の贈り物習慣にあった値札ごとプレゼントするにならって、無料で作れるものに価格を自分でつけて贈るというのは如何でしょうか?
例えば多くの会社では見込み客の獲得のために、
「失敗しない〇〇選びのポイント」
「〇〇業界の入門書」
「〇〇サービスの各社比較」
などの資料をウェブサイトで無料ダウンロードできるようにしています。
これらの資料は社内リソースを使い、かなりの時間をかけて作成し、定期的に更新されているものもあり、人件費を考えれば数十万円のコストがかかっていることも珍しくありません。
これらの資料を「販売価格19,800円」と値付けしたうえで、この情報が役立ちそうなお客様にメッセージを添えてプレゼントするのです。
Youtubeをはじめネット上には無料でアクセスできる情報があふれています。
もしかしたら、あなたが作成したレポートの情報の出典も、無料サイトに掲載されているかもしれません。ただ、ただ、その玉石混交の情報の中から、専門家であるあなたが精選した情報は、それだけで付加価値が生まれています。
また送り先が必要(読むべき)だと思う理由を添えてあげれば、相手は
「自分のことを気にかけてくれているんだな。しかも19,800円の価値があるものをもらった」
と感じてくれるかもしれません。
野村義樹 プロフィール

愛豊通信科技(上海)有限公司 副総経理
中国駐在員に人気のメルマガ「中カツ!通信」の配信者
1978年、東京生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒。政府奨学金留学生として天津の南開大学に留学。日本帰国後コンサルティング会社に入社。台湾、深センの駐在を経て、カゴメ株式会社に転職し中国での食品事業、EC事業、食堂事業に携わる。その後、現職にてシニア向け事業の立ち上げ後、コールセンター、EC代理運営、BtoB営業支援を日系企業、欧米企業、中国企業向けに提供。
毎週、中国市場を面白く紹介する「中カツ!通信」を3,000名以上の登録者に配信。約20年に渡り中国の発展を見てきた経験と「現場」の情報は、記者やエコノミストも注目している。