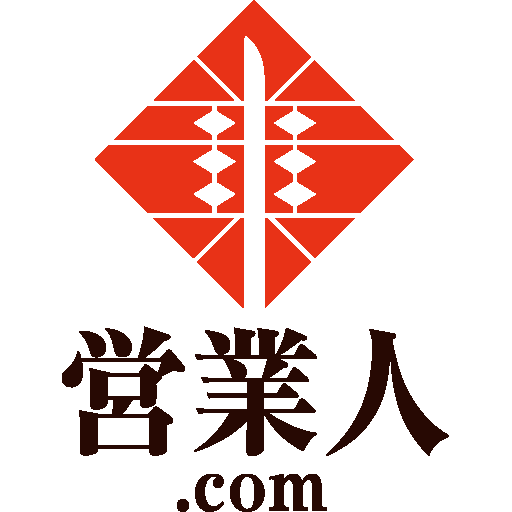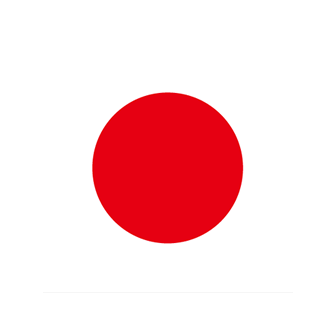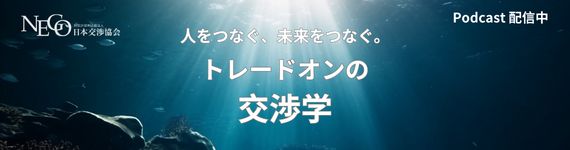Vol.33 競合と比較した優位性を訴求するスキル―FABE話法

本コラムは営業経験が2年から5年程度のB to B営業パーソンを対象としています。時代とともに営業のやり方は変化しますが、営業の本質である「量×質」という成功法則は不変です。ここでは、営業力強化につながるパーソナルスキルについてお伝えします。
FABE話法は顧客に自社製品・サービスを強く印象付けるスキル
Vol.31の「伝える力の基本」では、ロゴス(論理)・パトス(感情)・エトス(信頼)の3要素をお伝えしました。今回もその中のロゴス(論理)に焦点を当てた、実践的フレームワークである「FABE話法」の活用について考えます。
FABE話法は、商談中の応酬話法で力を発揮するスキルです。特に、競合他社と比較した優位性を訴求することで、自社への関心が薄い顧客に対して興味関心を引くことを目的に活用します。
FABE話法とは?
FABE話法は次の4つで構成されます。
• F(Feature):特徴
• A(Advantage):優位性
• B(Benefit):便益
• E(Evidence):証拠
この構造を意識することで、顧客からの「それで、他社とどう違って、弊社にとってどんなメリットがあるのですか?」と聞かれた際に簡潔に回答でき、自社製品・サービスの優位性やその便益を強く印象付けることができます。
商談の初期段階で顧客の興味関心を喚起できず、顧客の具体的な課題のヒアリングへ発展することができない営業パーソンは、自社の優位性を伝えていないか、相手にとってわかりやすく伝えられていないことが原因の1つとして考えられます。営業パーソンと顧客との情報格差がない現在のビジネス環境では、ただ自社製品のスペックを説明するだけでは、顧客が興味を持つことはあまり期待できません。このような状況では、顧客の関心を引くための「きっかけ」を提示できるかが重要です。FABE話法は、「まずはこの点でお役に立てます」と端的に伝える構造を持つため、興味を示していない顧客との商談を次のステップへ進める突破口として機能します。
FABE話法の活用シーン
FABE話法は、商談において「自社の特徴を明確に伝え、興味を喚起する」ために有効です。特に以下のような2つの状況で力を発揮します。2つのシーンに共通する目的は、「顧客の選択肢の中に、自社を入れてもらうこと」です。
① 顧客が他社製品を利用中、もしくは導入を本格的に検討している場合
この場合は、顧客が他社の製品・サービスにどのような評価をしているか、検討のポイントは何かを丁寧にヒアリングしたうえで、自社の「差別化ポイント」を訴求します。特徴だけを並べるのではなく、「何がどう違い、それが顧客へどう役立つのか」を明確に伝えることが鍵です。
② 顧客が現状維持を選択しようとしている場合
顧客が「今のままで特に困っていない」と感じている状況でも、FABE話法は有効です。例えば、営業管理システムを使用せずExcelで管理している企業など、現状に大きな不満はないものの、将来的な改善の必要性はなんとなく感じている顧客に対しては、「今は見えていないが、導入によって得られる便益」に目を向けてもらうアプローチが効果的です。営業パーソンが「あるべき姿」を仮説として提示し、そのギャップを埋める手段として自社製品がどのような優位性を持ち、どのような便益をもたらすのかを具体的に示すことで、顧客の興味を喚起し、現状維持から一歩踏み出すきっかけをつくることが期待できます。
ここで強調をしたいことは、効果的にFABE話法を活用するためには「顧客理解をすること」が必要であることです。商談ではまずヒアリングを通じて、顧客の状況・懸念・検討ポイントを把握し、その上で伝えるからこそ納得感が生まれます。応酬話法は、質問話法とセットで捉えることが大切です。
FABE話法事例
営業管理システムとしては市場認知度の低いシステム(以下、システムKと記載)を、専門営業管理システム検討中の顧客に訴求するケースを例に考えます。
システムKは、プログラミング知識不要で誰でも簡単にアプリケーションが開発できる手軽さが特徴です。市場の認知度は一定程度ありますが、営業管理という領域で応用できることについては認知されていません。
商談を通じて下記の状況を聞き出しました。
■ 全社的に「DX」がテーマとして挙がっている中で、営業管理システムの導入が必要となっている。
■ 親会社がS社のシステムを利用しており、それを中心に検討中。
■ 現在S社と導入検討のための打ち合わせをしているが、営業業務を全面的にシステム化するS社のシステムは自社にとって少し過剰であると感じている。
■ 特に、社員が使いこなせるのかということを心配している。
■ 最終的には複数のツールを検討しなければならないが、世の中に営業管理システムが多すぎてどれを選択肢に入れれば良いか迷っている。
このような状況下で、システムKを検討の選択肢に入れてもらえるように興味関心を示してもらうトークとして下記が考えられます。
• F(特徴):システムKは、プログラミング不要で誰でも簡単にアプリケーションを開発できます。
• A(優位性):営業業務全体をパッケージ化されているため検討から導入まで1年以上かかるS社とは違い、システムKは特定の領域だけをシステム化するスモールスタートができるため、導入期間を短くできます。
• B(便益):例えば、見積もり書のデータベース化といった、どんな営業組織でも優先順位の高い課題から段階的に対応できるため、現場への負荷が少なく、早期に効果が実感できます。
• E(証拠):A社では、検討から3か月で導入を完了し、見積もり書のダブルチェック機能を実現したため見積作成のミスが無くなり、導入前に比べ粗利率が向上しました。
FABE話法を使いこなすためのポイント
FABE話法を使いこなすためには、次のポイントを意識することが重要です。
【準備段階】
まずは自社理解を深めることが重要です。その範囲は、自社を取り巻く環境までを指します。競合を列挙し、自社との違いを知る必要があります。
自社の優位性や便益を伝えるうえで、過去の導入実績を学ぶことは非常に有効です。気になる事例があれば、その案件を担当した営業パーソンに導入の経緯を確認し、背景・課題・解決策・成果といった流れで整理しておくと、トークに活用しやすくなります。
整理した事例は、以下の2つの視点から応用展開できるようにしておくと、FABE話法の説得力が格段に高まります。
【1】業界カテゴリで抽象化する
1社の事例を複数のターゲットに応用するには、業界や業種の上位カテゴリに置き換えることが効果的です。
たとえば、トヨタ社での実績を「自動車業界」や「製造業」として整理しておけば、他の業界でも共通項として活用しやすくなります。
• 例:「トヨタ社では〜」→「製造業のお客様では〜」
【2】共通の「あるある課題」を起点に展開する
背景をその企業特有のものとして捉えるのではなく、業界全体に見られる傾向や構造的課題として整理することで、他の顧客にも刺さる「汎用ストーリー」に変換できます。
• 例:「見積書がデータベース化されておらず、引継ぎに時間がかかる」
→「営業担当者の異動や離職が多い中、顧客とのやりとりを組織として共有しておく必要がある」
このように、「営業組織に共通する課題」として提示することで、初対面の顧客にも「この営業はよくわかっているな」と感じてもらいやすくなります。
【商談での実践】
顧客の利用製品・サービス、判断基準、導入や導入検討の背景などをヒアリングしたうえで、FABEのフレームに沿って比較の軸を定める必要があります。顧客の利用状況は公開されていないため、事前に把握することは出来ません。そのため、商談でヒアリングをしたうえで、FABEのフレームに整理ながら応酬話法を展開する必要があります。
同じ会社組織に属していても、役割(職種や職位)によって便益は変わることを知っておく必要があります。例えば、購買部門はコストメリットを求め、現場担当者は使い勝手や導入負荷の軽減を重視します。このように、商談相手がどのような役割かを見極めてトークを展開する必要があります。
【マインドセット】
「何が違うか」よりも「顧客に対してどんな点で役立つのか」に意識を向けることが重要です。これにより、顧客視点のトークになり、「売り込まれている」という印象を軽減することができます。
FABE話法は単なる「話法」に留まらず、自身の「市場理解の結晶」
他社利用中並びに他社導入を検討中もしくは、現状維持を希望する顧客との商談で、自社に興味を示してもらうということはとても難しいことです。しかしながら、FABE話法を体得することで、その難しい状況を打破する可能性が高まります。FABE話法は、一見シンプルな構造に見えますが、実際に商談で効果的に使いこなすには高度な状況判断と準備が求められます。
また、FABE話法は、顧客に興味を持たせる話法であると同時に、自分自身が「顧客に対して何をどう伝えるべきか」を考えるプロセスでもあります。先輩や上司から、自社の導入実績や成功事例を教えてもらう際には、ただその情報を暗記するのではなく、FABEのフレームに整理することをお勧めします。このような地道な作業ができれば、説得力のある営業トークができるようになるでしょう。
筧 裕介 プロフィール

トランスエージェント上海 総経理
愛知県出身 信州大学卒業
大学卒業後役者となるため劇団ひまわりに入所。
その後は舞台を中心にドラマ、レポーター、イベントMCなど多岐にわたって活動をする。
09年トランスエージェントに参画し、同年7月末に上海赴任。
10年には営業人材適性診断「王牌」や営業人材向け勉強会「王牌商道会」を立ち上げ、中国日系企業の営業人材の採用・育成のサポートを開始する。
2014年に総経理に就任し、現在は産業材市場に特化したウェブマーケティング支援及び営業組織管理支援(SFA導入)まで事業領域を拡大し、中国進出日系企業に対してB to B営業・マーケティング支援事業を展開している。